皆さまこんにちは。水壁でございます。
今回はコラムと題し、小話をしていこうかと思います。内容としては雑記などや考え方で書いていたことに近しいものになりますが、雑記ほど雑多でなく、考え方ほど思想に依ってない、そんな内容で行きますのでよろしければ最後までお付き合いいただけますと幸いです。
新書とは
記念すべき第一回目、内容は新書の読み方でございます。
皆さんはコンビニや本屋の端っこなどで、妙に薄い文庫本のような本を見かけたことはないでしょうか?
手に取ってみるとイメージする文庫本よりも縦に長く、装飾の少ない装丁の物が多いですね。
そうです。これが新書と呼ばれる本になります。
新書はジャンル名ではない
印刷業などに詳しい方であれば、よく知っているとは思いますが、新書は発行形式を指すものでジャンルを言及するものではないです。
ただ通常、本といわれて思い浮かべるような文庫やハードカバー製本などに比べ、安価且つ内容が堅苦しくないことが多いです。特にハードカバー製本なんかと比べれば重量も全然違うのでコンビニなんかでも扱いやすいという側面もあったりします。
じゃあなんで新書の読み方なんて書き方?
前項で「安価」と言及したと思いますが、新書で出る本は所謂専門書と比べて「これ本当に内容精査したのか……?」となるくらい条件や思想が偏っていたりします。このあたりで手間賃減らして安価になっているのか?と疑うくらいに。
もちろん入門書としてよくできているものもありますし、平等な視点で語られているものもあります。ですが鵜呑みにできるほど信用はおけない。というのが私の意見です。
なのでこのブログで新書を紹介する前に、多少の注意喚起ができるように書き始めた、というのがこのコラムの正体になります。
気を付けるべき点1:話半分に読む
次回紹介しようとしている古本が思いっきりこれに当てはまります。
新書では、共著という形はあまり見ません。大学の先生が研究の傍らで出版していることもあるくらいなので、まあさもありなんというところでしょう。
するとどうなるか。前項で言及したように、どうにも偏った視点で物事が語られていることがあるんです。
本を出すような人ですから、一定程度の知性をお持ちではあると信じたいですが、どうも断言する文体であることが多いです。「え?それデータもなしに断言しちゃだめでしょ?」って文もそこかしこに。
なので、新書に限った話ではないですが「こういう人もいるんだなあ……」くらいの話半分に聞いておくのがベターです。
気を付けるべき点2:一冊で判断しない
これも前項にかかわる事柄ですが、どうしても視点が偏るので、同ジャンルで複数の著者の物を読むことをお勧めします。
せっかく安価なので、啓発系や哲学書のようなもの、入門書のようなものであれば複数買って比較してみることが大事です。
雑学系はここに当てはまりません。好きに買って好きに読めばいいと思います。
気を付けるべき点3:よさそうな本だと思ったら早めに買う
これは別方向で気を付けるべき点ですね。よほど名著だ、ということでもなければ新書は発行部数が多いこともあって、すぐ置かれなくなっていきます。
見かけたら早めに行動するのが吉です。
終わりに
今回はコラムとして新書の読み方についてお話していきました。
次回は古本の紹介を挟みまして第二回に続けていこうかと思いますので、よろしければまた次回も見に来てもらえると幸いです。
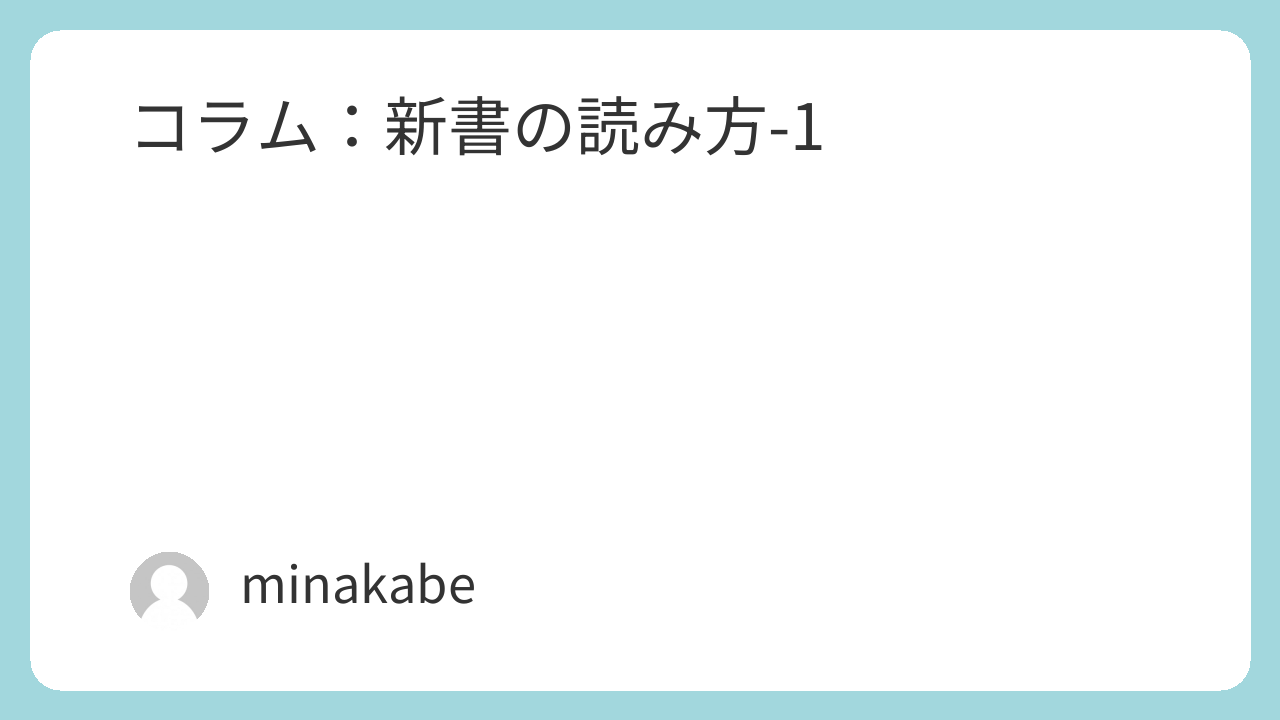
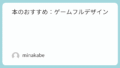
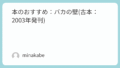
コメント